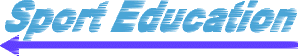
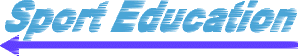
| No.5 | S.K |
|---|---|
|
私は体育をするのが約1年ぶりで、みんなについていけるか心配だった。でも、大好きなバドミントンができてとても楽しかった。 中学生の時、部活でやっていたので、昔(?)を思い出してなつかしくなった。 授業では、初心者からとても上手な人まで、さまざまな人がいた。また、環境科学部と合同だったので、新しい友達ができてよかった。 チームですることが多かったので、班の人たちも上達の様子を見て、感心していた。班で協力して弱点を克服していったのも楽しかった。 みんな真剣で、高校の体操服を着て気合いを入れていた。 試合では、負けることもあったけれど、男子のペアに勝てたときはとてもうれしかった。 バドミントンは力だけのスポーツではないんだと思った。私はドロップやヘアピンが好きで決まったときは、うれしかった。 バドミントンを通して、一番思ったことは、体力の衰えである。一回目の授業の後の筋肉痛はスゴかった。4,5日は治らなかったのをよく覚えている。でもその痛みは少し心地よかったかも・・・(?) また、運動するとすぐに疲れてしまう。体育は1年の前期しかないけど、これからも適度の運動を続けた方がいいと思う。 バドミントンによって学んだことは、一生懸命スポーツをすることの楽しさだと思う。上手・下手関係なく、みんなで楽しめてよかった。今度からは卓球をがんばろうと思う。 |
|

|
|
| No.6 | J.K |
|
私は中学校のとき、バドミントン部に入っていた。だから一通り、バドミントンの技術は身についていたし、ルールも知っていた。 何人か、バドミントンの経験者がいて、経験者と、未経験者を比べてみると、やはり経験者がダントツで上手だと思った。 バドミントンは、コートもせまいが、瞬発力や、持久力がとても必要とされるスポーツで、体力がなければとても続かない。経験者とのシングルスの試合では体力がなければ続かず、とてもつらい思いをした。 やはり、しばらく運動をしていないと体がすごく衰えるものだなぁ、と思った。しかし、バドミントンの試合や、友達と1対1で打ち合うのはとても楽しかった。 私が組んでいた友達もまた、中学、高校、とバドミントンをしていた人だったので、打ち合いをしても、ずっと続くし何よりもやはり楽しかった。 その人は私よりも上手だったので、私は「負けたくない。」と思った。久しぶりに本気でバドミントンをやれてとてもよかったと思う。 今回、バドミントンでは6つのチームに分かれていた。チームはかなりランダムに決められていて、私は、8人のチームだったが、その中で知っている人は、1人しかいなかった。 入学してすぐのころだったのだから、当然といえば当然だったのだが、楽しくやっていけるだろうか、ととても心配だった。 でも、そのチーム8人の中でペアを組んだり、戦ったりと、いろいろしているうちに、いつのまにか仲良くなっていた。 新しい友達も増えてうれしかったし、他チームと対戦するときも、その試合などを通して友人が増えていった。 私は、高校ではバドミントン部に入らず、別の文化系の部活に所属していた。バドミントンをしたのは本当に久しぶりだった。 3,4年ぶりにやってみて思った事は、昔の現役時代のようにはいかないなぁという事、昔できた事が今できないこと、無理をすると、翌日筋肉痛になってしまうという事だった。 プランクがあるとやはり大変だ、と思いつつ、みんなで楽しくやれて、よかったとも思った。 |
|

|
|
| No.7 | T.E |
|
バドミントンを通して学んだことは、勝負で勝つためには、しっかりした連携をとることが必要だということである。 ダブルスの試合で、特に難しい球ではないのに、連携ミスで失点することがあった。そのときは、声を出して、どちらが返すのかハッキリさせる必要がある。もちろん無言でも試合はできる。しかし、それでは、勝つことはできないだろう。 これは、バドミントンに限らず、他の様々なスポーツに当てはまるだろう。ダブルスで勝利するためには、連携をとる、特に、初心者で、チームを組んで間もない同士は、声によるコミニュケーションが試合の流れを呼び、とても重要であると学んだ。 次に、私は、授業中に次のような場合に出くわした。ダブルの試合で、相手チームに点数が入ると、相手の選手は、私が見る限り、過剰に喜ぶのである。自分がミスをして相手に点が入ると、その喜び方は、他のどのチームよりも際立っていた。 たまたまその人が喜怒哀楽が激しくて、全く意識していなかったのかもしれないが、私と私のパートナーが腹を立てたのは事実だ。しかし、私は、この出来事を批判しているのではない。私自身、勝敗を決める試合では、技術・体力だけでなく、心理的・精神的な面も大事だと考えている。 つまり、挑発するような言葉によって、相手をイライラさせたりすることは必要だと考えていた。 ところが、私自身がその経験を、2対2の少人数の試合の中でして、今までの考えに疑問をもった。相手の心理をつく言葉は、スポーツに必要なのだろうかと考えた。 ちょうど平行してW杯サッカーが開催され、日本のホームで真剣勝負を身近に見ることができた。韓国は、ホームの利も手助けして、ベスト4まで進んだ。ホームの利とは、大衆の応援、相手へのブーイングなど、心理的・精神的な面であろう。 一方、決勝戦をするのは、アウェイの不利を勝ち抜いたブラジルとドイツで ある。 勝負では、プロでもアマでも、練習試合でも親善試合でも、たとえ大学の授業の試合でも初めから負けるつもりでやっているのではなく、勝つための試合である。 私は、その点に気づき、相手の喜びに苛立つ精神的弱さを知った。心理的・精神的強さは、技術・体力と同じように大切だと思う。 |
|

|
|
| No.8 | S.M |
|
バドミントンによって得たもの、学んだこと バドミントンをやって、バドミントンはどのように攻めたらいいのかがよく分かった。 バドミントンでは、前後のゆさぶりが大きな効果を持っているなと感じた。 実際に試合をやっていても、うまい人ほど大きなショットと小さなショットを使い分けていたし、中途半端な長さには打っていなかった。まあこれは、技術の問題もあるけど、戦略的に強く感じたことだった。 次に、ダブルスをやってて感じたのは、2人のいきが合うかどうかが大きな意味を持つことを強く感じた。役割分担がしっかりできていれば無駄な体力を使わずに効率良く試合ができるし、スペースをあけずにすむからだ。 これはどのスポーツでも同じだけど、改めてコミュニケーションの大切さを感じた。 そして一番良かったことは、バドミントンのおもしろさが分かったことだ。今までに何度か遊び程度にはやったことがあったけど、今回真剣にやってみて、とてもおもしろかった。 練習しているうちにだんだんうまく打てるようになったし、試合でもいい試合ができたので、バドミントンへの興味が強くなった。 あと実際やってみて思ったのが、バドミントンは見た目以上にハードなスポーツで、体力がないと最後の方は試合にならないくらい疲れてしまうことだ。 こんなにきついとは思わなかったので正直驚いたけど、楽しくやれたのでよかった。 |
|

 BACK
BACK

 NEXT
NEXT