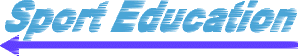
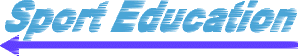
| No.37 | T.S |
|---|---|
|
私が一番充実することができたのは、ダブルスで真剣勝負をしていたときだった。真剣勝負とはいっても、大学の授業であるから、それほど試合のレベルは高くなかっただろう。しかし、そんな中でも、自分の持ち味である“読み”をいかに活かすことができるか、自分なりに試してみたかった。本音を言えば、まだまだダブルスの試合を通して試してみたかったことがいくつかあったが、2日間のうちだけでも随分と自分が思うようなプレーができたので、おおむね満足している。 あくまでもこの授業のメンバーの中で考えた場合だが、自分の持ち味である相手を観察する能力と、味方を活かす能力は、十分試合で使えると思っていた。幸いにもペアの女の子が左利きで能力のあるコだったので、自分の思うようなプレーは随分スムーズにおこなえたと思う。 自分の能力を考えると、自分一人で試合を決めていくようなタイプではない。だから、いかにして相手のバランスを崩すか、いかにして味方の能力を引き出すことができるか、に焦点を置いた。シングルスでは目立った動きをとることはできなかったが、ダブルスではある程度いい勝負が出来ると思っていた。なぜなら、ダブルスは二人の動きがかみ合うことで、予想以上の力を出せると信じていたからだ。ではまず、試合中に気をつけていたことを挙げてみよう。
ペアの彼女の能力を考えれば、自分がそれだけを気をつけていれば、ある程度試合の主導権を取れると思っていたし、案の定勝率も高かったと思う。ま た、回を重ねるにつれ、味方の動きも読めるようになり、バランスを取りやすくなったことで、予想以上の力を出すことができたのではないだろうか。 自分は、物心がついたときから高校までずっと野球を続けてきた。もちろん、野球はするのも見るのも大好きだ。特に守備の方には定評があったし、自分も守備に関しては、自信を持っていた。特に、味方投手の特徴、配球、相手打者の特徴、作戦などから、あらゆる選択肢の中から自分なりに予想して守備位置を考えることは、とても楽しかった。 自分はこういったことが好きであり、またそれなりに、これは比較的他人より優れている能力だろうと思っていた。そうした能力が、こういった機会で試すことができてよかったと思う。 個人的には、サッカーという広いフィールドで試したかったが、バドミントンでも十分に楽しむことができたからよかったと思う。今後、環境科学部の友達同士で遊びのサッカーグループを作ろうとしているので、その機会に、味方を活かし相手の持ち味を消すようなプレー(味方を活かして自分も活きるようなプレー)など、いろいろ試すことができたらいいな、と思っている。 |
|

|
|
| No.38 | J.D |
|
私は、小さい時からスポーツが大好きでした。理由は、スポーツを一緒にすることによって、周りの人達ともうち溶けることができるし、ストレス解消にもなって気分がスッキリするからでした。 今回のスポーツ演習「バドミントン」もそれをしたことによって、なかなか知り合うきっかけのない他学部の人達と知り合えたし、いやな気分の時も、バドミントンをすることによってストレスを取り除くことができました。 私が今回の演習で一番印象に残ったことは、私達のチーム「レインボー」が、第1回目の試合の時は5位であったにもかかわらず、第2回目の試合の時は、2位になることができたことです。これは、「チームで勝つ」ということをみんなで目指した結果でした。実際私達チームが勝った試合は、3−2がほとんどで、試合が始まる前に「あの相手には、どういう方法でなら勝てそうか」などをみんなで考えたおかげで勝てたのだと思います。 私は、バドミントンはあまり上手くなく、どうやったら「チームで勝てる」のかを考えた末、チームのみんなを精一杯応援し、審判のカウントが聞こえずらかったり、うやむやだとプレーしている人がやりにくいので、審判のカウントは大きな声で解かりやすく言うように心がけました。きっと私の審判のカウントの仕方や、大きな声の声援も、チームの勝利に貢献できただろうと思います。私達のチームは、1人1人は“特別に上手い”という人はほとんどいなかったのですが、最終的には2位になれ、「みんなで1つの目標(私達の目標は優勝でした)に向かってがんばれば、個人で戦うよりも大きな力を出すことができる」ということを身にしみて感じました。 これは、スポーツに限らず、 勉強や日常生活のいろいろな場面で役立つことだと思うので、これからの生活で役立てていきたいと思います。 |
|

|
|
| No.39 | C.K |
|
私は高校の体育の授業でバドミントンを習ったことがあるけれども、その時は何度練習してもなかなかうまくできなかったこともあり、いつも体育でバドミントンをやるのが嫌だった。でも、バドミントン自体は嫌いではなかったので、大学のスポーツ演習でバドミントンが選択できると分かった時は、少し迷ったけれど、「もう一度やってみて、前よりも少しでもいいから上手になりたい」という気持ちがあったので、バドミントンを選択した。 最初は久し振りに運動をしたので「90分間体を動かす」というのがとてもきつくて辛かったけれど、回を重ねるごとにそれはあまり気にならなくなったし、毎回とても楽しく練習できたと思う。 私は、アンダーショットやスマッシュが最初には全く出来なかったけれど、チームの友達に教えてもらうことで少しずつできる様になった。 後半は試合が多かった。私は、自分のミスが重なって負けることが多くて、悔しかったけれど、いつも「次頑張ろう」と前向きに考えることができたので、とても良かったと思う。最後のリーグ戦の時はチーム6人が一つになってみんなで頑張れたのでとても楽しかった。私たちのチームは誰かが試合をしている時、試合をしていない人は試合をしている人がいるコートのところに行って声を出して応援していた。 このバドミントン演習を通して得たものは、私は友達だと思う。私は福岡県出身で、長崎大学に入学した当初は友達ができるかどうか心配でたまらなかった。また、私の履習番号は環境科学科の中では前半の方なので、番号の近い前半の方の人達とは他の講義をほとんど一緒に受けるので、友達になれたが、後半の方の人達は全くと言っていいほど知らない人達だった。しかもバドミントンには私が親しくしていた人達が全くいなかったので、最初は不安だった。でも、練習を通して今まで話したこともなかった後半の方の人達や環境科学部に在籍している中国人留学生、同じ学部ではないけれど、保健学科の人達とも話す機会が得られた。特に同じチームだった5人とは同じ環境科学部ということもあり、とても仲良くなれて、毎回みんなで楽しく練習できていたと思う。特に中国人留学生の2人とは、最初は全然しゃべれなかったけれど、しだいにしゃべれるようになり、今では、スポーツ演習の時間だけでなく、普通の大学内で会った時も挨拶したり話したりできるようになった。高校の時はそういったことがなかったので、やはり大学だなぁと思うことがある。 今回のバドミントンでは、技術的なことだけでなく、友達とのつながりも得られたので、とても良かったと思う。 |
|

|
|
| No.40 | Y.T |
|
バドミントンは自分が最もうまくできる種目であった。それゆえ、スポーツ演習でバドミントンを選択した。 僕は、バドミントン以外の種目でも誰かとペアを組んだり、チームを作ったりする時、仲間がどう動いて、自分がどう動けばいいのかがよくわからないため、一人で行うほうが気が楽であった。 しかし、今回バドミントンを選択し、そして、ダブルスのペアを組んで、少しだけ、どう動けばいいかわかった。もちろん、相方をつとめた人が上手でこちらがどう動けばいいか分からない時もきちんとフォローしてくれたからそう感じたという点もあるが、声をかけ合って互いの動きを決めるやり方が身についたからだという理由もある。 このやり方を身に付けて相方とコミニュケーションを取り、試合をうまくやれるようになったことが、今回のバドミントンの授業によって得たものであると言える。 |
|

 BACK
BACK

 NEXT
NEXT