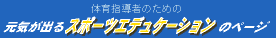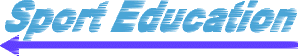
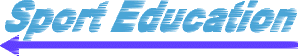
5.最後に・・・ 2002年前期 木2クラス受講の皆さんへ木2クラスの皆さんは、私が事前に予想していたより遥かに優れた取り組みをしてくれました。私は時々教員として伝えるべき情報をしっかり伝えているかどうか不安に思っていましたが、その心配はほとんど無用で、私が指示したことを2倍3倍の密度でやってくれていたようです。今回皆さんに取り組んでもらった「学習の記録」や「小レポート」は、私の中ではどちらかというと付随的なもので、皆さんの「学習や興味の流れを漠然とでもつかめたらいいな」くらいの軽い位置づけとしてありました。しかし、この取り組みは結果として皆さんの目標を確認させ、全体的な学習活動を促進し、私自身にも皆さんの実情を知らせてくれる極めて重要な機能を果たしたようです。また私がこのホームページを思いつくきっかけも与えてくれました。このホームページは皆さんの「生の言葉」が不可欠の要素としてありますが、そのような情報を集めることができた境遇に心から感謝したいと思います(※)。 授業中私はできるだけ素知らぬ顔をしていましたが、実は"ブラボー"と叫びたくなるような瞬間が何度もありました。レポートを読んでいる時も、うれしくなり一人で感動することたびたびでした。今回の皆さんの取り組みが、私が採用した"スポーツエデュケーション環境"とどの程度関連していたのか今のところ詳細には分かりませんが、いずれにしろ、皆さんと過ごしたこの15週間は私にとって極めて貴重な体験となりました。ありがとう。「卓球」の期間も短いながらそれなりに充実していたと思います(実は他にもいくつかやりたいことがあったのですが)。 さてそろそろ次に取りかからないと行けません。今回の成果も、見る人が見れば客観性の問題をクリアしているとはいえないでしょう。場合によってはスポーツ教育に科せられた「社会的使命」の一つ目の低いハードルを越えた段階に過ぎない(またはそこまでも行っていない)かも知れません。いずれにしろこの先には広大な未開の土地が眠っているのです。前に進むしかありません。今回は、最後に、大きく叫んで終わりにしましょう。長崎大学2002年前期スポーツ演習「バドミントン」木2クラスのみんな、ブラボー!! そして、スポーツエデュケーション、バンザーイ!! ※補足: |